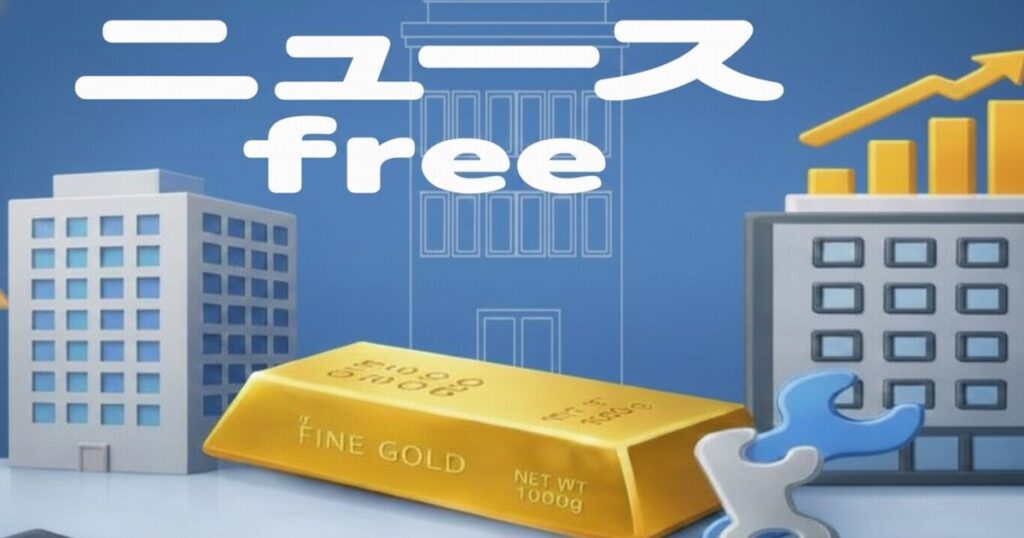日本の高速道路におけるETCシステムは、長年にわたって渋滞緩和や利便性向上に貢献してきました。
しかし、台湾の先進的なETCシステム「eTag」と比較すると、いまだ多くの課題が残されていることが明らかになります。
本記事では、台湾の取り組みを紐解きながら、日本のETCが今後どのように進化すべきかを考察します。
ETCシステムの進化と台湾との差
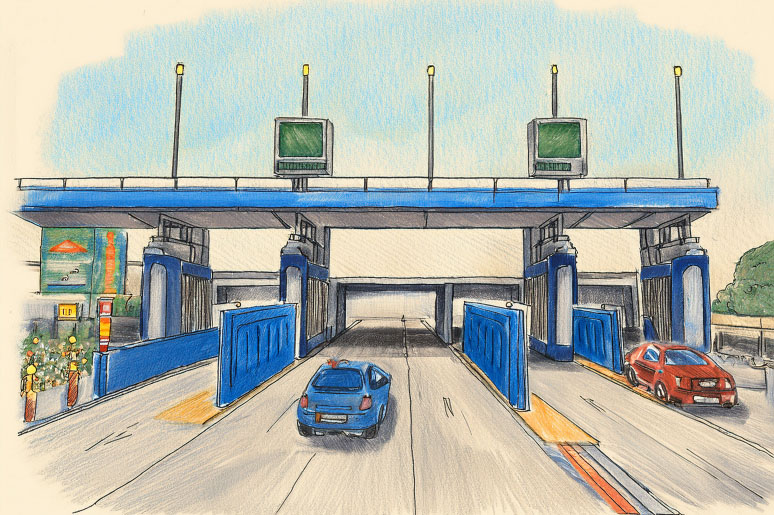
ETC(Electronic Toll Collection)は、高速道路の料金所で車を止めずに通過できるシステムとして、2001年に日本で導入が始まりました。
以降、ETCは着実に普及し、現在では利用率が90%を超える状況となっています。
一方、台湾では2013年に世界初の「全電子式多車線フリーフローシステム」が導入され、「eTag」と呼ばれるシンプルかつ革新的な技術で料金徴収のデジタル化を成功させています。
日本と台湾、同じアジアの先進国でありながら、ここには大きな技術差と運用上の発想の違いが見て取れます。
台湾のETCシステム「eTag」の特徴と運用方法
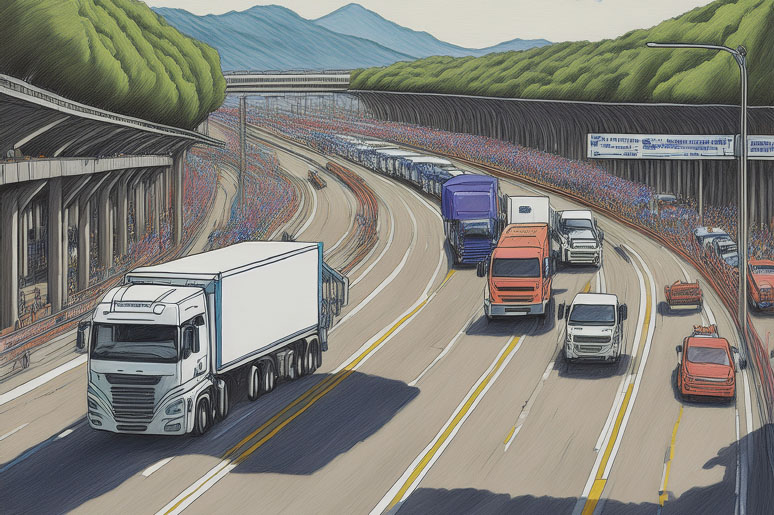
車載器不要、選択制の「eTag」タグ

台湾では、車両に取り付けるのはETC車載器ではなく、スマートタグ「eTag」です。このタグはFETC(Far Eastern Electronic Toll Collection)によって発行され、窓に貼り付けるだけで使用できます。
しかも、このタグは義務ではなく、任意で利用可能です。
もしeTagを装着していなくても、ナンバープレート認識技術によって走行記録が自動的に記録され、利用者には後日支払い案内が送られます。
支払いはオンライン、ATM、コンビニなどで可能であり、柔軟な選択肢が用意されています。
料金所の完全撤廃
台湾の高速道路では、料金所という物理的な構造物は一切存在しません。
代わりに、道路上に設置された高架ゲートにより、走行車両の情報を読み取り、通行料金が自動的に計算されます。
車両は減速することなく通行できるため、渋滞の原因が根本から排除されています。
この仕組みは「フリーフロー」と呼ばれ、世界中で注目を集めています。
距離連動型課金と割引制度の充実
台湾では、走行距離に応じた課金方式を採用しており、利用者は「使った分だけ支払う」という極めて公平な仕組みになっています。
さらに、一定距離以上の走行に対する割引制度や、通勤時間帯の割引など、生活スタイルに合わせた優遇策も導入されています。
このような柔軟な料金体系は、利用者の利便性を高めると同時に、公共交通とのバランスを図る上でも非常に効果的です。
高い信頼性と運用効率
2013年の導入以降、eTagシステムは大規模な障害もなく安定稼働を続けており、信頼性の高いインフラとして社会に定着しています。
保守や運用にかかるコストも大幅に削減され、行政と民間企業の連携によって持続可能な運用モデルが確立されています。
日本のETCシステムが抱える根本的な課題
ETC車載器への依存と初期コスト

日本ではETC車載器の装着が利用の前提となっており、新車購入時や後付け時には数千円から数万円の費用が発生します。
この費用がETC普及の障壁となっているケースも少なくありません。また、車載器が故障すれば、その影響は全国に波及します。
このようなハードウェア依存型の設計は、メンテナンス性や将来的な技術更新の面でも課題が残ります。
料金所の存在と通行の物理的制約
現在の日本の高速道路には、依然として物理的な料金所が多く残っており、一部にはETC専用レーンが設けられているものの、完全なフリーフローには至っていません。
これが渋滞や通行時の減速を引き起こし、事故の原因ともなっています。
料金所という存在そのものが、道路インフラのデジタル化を妨げる障害となっているのです。
システム障害に対する脆弱性
2025年4月に発生したETCシステム障害では、全国で約110箇所の料金所が一時的に停止し、大規模な交通混乱が発生しました。
これはソフトウェア更新時の不具合が原因とされ、危機管理体制の不備も指摘されています。
日本のETCシステムは、高度に集中管理されている一方で、障害が発生した際の対応が後手に回る傾向があり、信頼性の面で課題が浮き彫りになりました。
柔軟性に欠ける料金体系
日本では、基本的に区間ごとの定額制が採用されており、台湾のような距離連動型や通勤割引、長距離割引などの制度は十分に整っていません。
利用者の多様なニーズに対応するには、より柔軟な料金体系が必要です。
台湾の事例から見える、日本のETC改善の方向性

車載器フリーへの転換
台湾のeTagに見られるように、ナンバープレート認識技術や低コストのタグ運用により、車載器の完全廃止が実現可能です。
日本もこの方向にシフトすることで、初期導入コストや維持管理の手間を軽減できます。
スマートフォン連携やクラウド決済との統合によって、よりユーザーフレンドリーな仕組みが構築可能です。
フリーフロー化による渋滞緩和
料金所を完全に撤廃し、フリーフロー型の高架ゲートを導入することで、通行時の減速や停車をなくし、道路全体の流動性が高まります。
これは物流業界にも大きな恩恵をもたらし、経済全体の効率向上に貢献します。
同時に、料金所の維持管理コストや用地費用も削減可能です。
公平で柔軟な料金体系

日本でも走行距離に応じた課金方式を導入することで、短距離利用者と長距離利用者の負担を適正化できます。
さらに、定期的な通勤者への割引や、災害時の一時的な無料化措置など、政策的に柔軟に対応できる仕組みが必要です。
危機管理体制の再構築
ETCシステムに限らず、社会インフラの多くは「止まらないこと」が前提です。障害発生時には即座に切り替えができるバックアップ体制や、民間企業と国が連携したシナリオ訓練が不可欠です。
台湾では導入当初からシミュレーション訓練が行われており、こうした点も見習う必要があります。
日本の交通未来を築くために必要な視点
日本のETCシステムは世界的にも評価される成功例ですが、技術進化のスピードやユーザー体験の多様化を踏まえると、さらなる進化が求められています。
台湾のeTagのような柔軟かつ低コストな仕組みは、日本の高速道路インフラを再定義するヒントとなるでしょう。
既存の制度を前提としたままの改良では限界があります。抜本的な構造転換こそが、次世代のスマート交通を実現する鍵です。
まとめ:台湾のETCから学ぶべきポイント
- 台湾の「eTag」は車載器不要で低コストです。
- フリーフローシステムで渋滞が発生しません。
- 距離連動型で公平な料金体系が整備されています。
- 割引制度が多様で柔軟性があります。
- システムの信頼性が高く安定稼働しています。
- 日本も構造的な見直しが必要です。