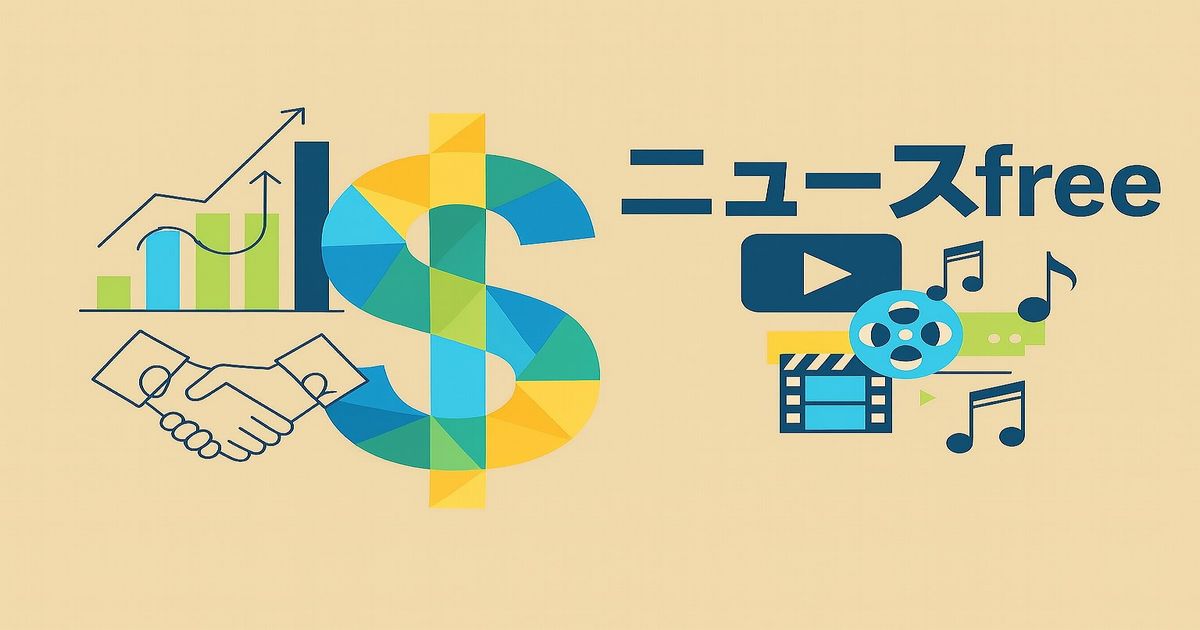近年、日本国内でスマートフォン利用者を狙う新たな脅威が発生しています。
それは、通信インフラを悪用した「偽基地局(IMSIキャッチャー)」による詐欺です。
東京都や大阪市などの都市部を中心に、一般市民のスマホが偽の電波に接続され、詐欺メッセージを強制的に受信させられるという深刻な被害が確認されています。
関連記事
本記事では、その仕組みから被害事例、各通信事業者の対応、そして私たちが取るべき対策までを網羅的に解説します。
日本国内で確認された偽基地局とは何
偽基地局とは、正規の携帯電話基地局を装ってスマートフォンとの通信を不正に傍受し、利用者の個人情報や位置情報を盗んだり、詐欺メッセージを送りつけたりする機器です。
英語では「IMSIキャッチャー」とも呼ばれ、その名称の通りスマホ内に記録された加入者情報(IMSI)を収集する目的でも使用されます。
都市部での確認が相次ぐ背景
東京都内や大阪市などの繁華街や駅周辺など、多くの人がスマートフォンを利用する場所で偽基地局の存在が確認されています。
背景には、不特定多数を一度にターゲットにできる地理的特性があり、訪日観光客を狙った組織的なフィッシング詐欺の可能性も指摘されています。
偽基地局が悪用する通信技術の脆弱性

GSM通信が抱えるセキュリティ問題
日本国内では使われていないGSM(第2世代)通信が偽基地局の主な手口として利用されています。
スマートフォンは電波を失うと自動的に接続可能な電波を探し、偽基地局が発信するGSM電波に接続してしまいます。
このGSMは暗号化が極めて脆弱であり、通信内容が容易に傍受される危険性があります。
電波妨害から通信誘導までの手順
偽基地局はまず、周囲の正規の電波をジャミング技術で妨害し、スマートフォンを一時的に圏外状態にします。
その後、自ら発するGSM電波に接続させ、スマートフォンに詐欺的なSMSを送信します。
多くのユーザーは端末が「圏外」からすぐに回復したように見えるため、不正な接続に気付かないまま詐欺行為のターゲットとなってしまうのです。
偽基地局によるSMS詐欺の実例と特徴

中国語のメッセージで訪日客を標的に
実際に送信されている詐欺メッセージは、簡体字中国語で書かれており、「海外でのカード決済が停止されたため、リンク先で確認してください」といった内容が多く確認されています。
リンク先には偽の銀行サイトやカード会社のログイン画面が設置されており、利用者が情報を入力すると個人情報が抜き取られる仕組みです。
中国大手キャリアを偽装する戦略
報告によると、偽基地局はチャイナモバイルやチャイナユニコムなど、中国の大手通信キャリアのIDを模倣しており、中国本土の通信環境に慣れている訪日観光客を狙っていることが分かっています。
この手口は、国内にいる外国人に対してだけでなく、技術的な知識に乏しい一般ユーザーも被害に遭うリスクを高めています。
通信キャリアと行政が講じる対策

通信事業者のリアルタイム監視
大手通信キャリアは、基地局間での通信ログや異常な接続を自動で検知するシステムの導入を進めています。
また、不審なSMSをフィルタリングする機能の強化や、セキュリティアプリとの連携なども強化されつつあります。特にAndroid端末向けにはGSM通信を手動で無効にできる設定も推奨されています。
政府による制度整備の必要性
警察庁や総務省も、IMSIキャッチャーによる違法通信を取り締まるための制度設計に着手し始めています。
しかし、現時点では日本国内においてIMSIキャッチャー自体を明確に規制する法律は存在せず、欧米諸国に比べて対応が遅れているのが実情です。
捜査機関の使用と犯罪組織の悪用の線引きも難しく、今後の法的整備が急がれます。
今すぐできるスマホセキュリティ対策

不審なSMSを開かないという意識
まず基本的な対策として、不審なSMSに記載されたリンクは絶対に開かないよう心掛けましょう。
通信キャリアや金融機関が個別にリンク付きメッセージを送ることは極めて稀であり、受信した際は公式アプリや公式サイトで確認するのが最も安全です。
設定とアプリで自衛手段を講じる
Android端末の場合は、GSM通信を無効化する設定が可能な機種もあります。
また、セキュリティアプリの導入により、不審な通信をブロックすることも有効です。
iPhoneなどでは設定の自由度が制限されているため、キャリア側の対応やアプリでの補完が求められます。
世界の対策と今後の課題

欧米で進む法整備と運用ルールの整備
アメリカやドイツなどでは、IMSIキャッチャーの使用を厳格に規制し、捜査機関でも使用には裁判所の許可が必要とされています。
一方で、技術革新の速さに法整備が追い付かないという課題も抱えており、日本でも今後は類似した運用ルールの導入が期待されます。
教育と啓発が重要になる時代へ
技術的な対策と同時に、利用者自身のリテラシー向上も欠かせません。
学校教育や社会人向け研修の中で、スマホのセキュリティやフィッシング詐欺への対処法を教える取り組みも今後必要になるでしょう。
デジタル社会における防御は、制度だけでなく「気付き」が支える部分が大きいのです。
まとめ
- 都市部で、偽基地局による通信詐欺が確認されています。
- GSMという古い通信規格が、悪用されています。
- 中国語の詐欺メッセージで、観光客が標的になっています。
- キャリア各社が、監視体制を強化しています。
- 自分でできる対策も、複数あります。
- 法整備と利用者教育の両面が、今後の課題です。