国家資格を持たない営業社員が医療現場でX線照射装置を操作していたという、衝撃的な事実が発覚しました。
問題の企業は米国系の医療機器メーカー、ニューベイシブジャパン。
内部では違法行為の証拠を残すなとする指示や、内部告発の抑圧とみられる行動も明るみに出ています。
関連記事
本記事では、事件の経緯と問題の本質、そして医療の安全性とコンプライアンスに対する社会の不安について詳しく考察します。
違法操作と証拠隠しの実態が表面化した背景

アメリカに本社を置く医療機器メーカー「ニューベイシブジャパン」において、無資格の営業社員が医療現場でX線照射装置を操作していた問題が明らかになりました。
医師や診療放射線技師などの国家資格を持たない人物が患者に対して放射線を照射することは、診療放射線技師法により厳しく禁止されています。
違反すれば刑事罰の対象となり得る行為です。
この問題が表面化したのは、社内の関係者からの内部告発がきっかけとされています。
複数の報道によれば、無資格の営業社員4人が整形外科手術の現場に立ち会い、医師の指示のもとでX線照射装置を実際に操作していたことが確認されました。
患者に放射線を照射する行為は極めて慎重な管理が必要であり、医療安全の観点からも極めて重大な問題です。
社長のメールが示す組織的隠蔽の疑い
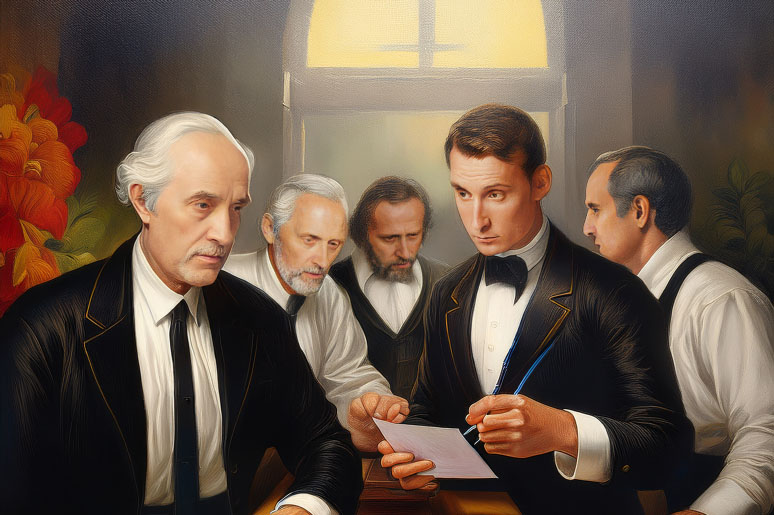
さらに問題を大きくしているのが、社内における証拠隠滅の指示とも受け取れる社長のメールです。
報道によれば、社長は違法行為の証拠となる写真や記録を残さないよう社員に指示していたとされます。
これは単なる個人の判断ではなく、企業としての組織的な対応である可能性が指摘されています。
内部告発者に対して圧力をかけ、事実の隠蔽を図るような対応が行われていた場合、企業のガバナンスと倫理の欠如が問われることになります。
こうした対応は社会的な信頼を損なうだけでなく、他の企業に対しても悪しき前例となり得ます。
診療放射線技師法に違反する重大性と法的リスク

診療放射線技師法では、医師や国家資格を有する技師以外の者が放射線を人体に照射することを禁じており、これに違反した場合は刑事罰が科される可能性があります。
今回のような営業担当者によるX線照射操作は、明確に法の趣旨を逸脱しており、単なる社内規則違反では済まされません。
企業側はすでに外部の弁護士を通じて事実関係の調査を開始しており、「当局からの協力依頼には全面的に応じる」としています。
しかし、信頼を回復するには不十分との声も多く、社会の目はより厳しさを増しています。
医療現場での営業活動の境界が曖昧に

医療機器メーカーの営業担当者が医療現場に立ち会うこと自体は、製品の使用説明や操作補助の観点から一般的なことです。
しかし、その範囲を逸脱して実際の医療行為に関与した場合、それは明確な法令違反となります。
とりわけ、X線装置などの高度な医療機器は人体に影響を与える可能性があるため、取り扱いには慎重を要します。
医療従事者と営業職の役割の線引きが曖昧になることで、患者の安全性が損なわれる危険が生じます。
内部告発者の保護が問われる現代の企業倫理
今回の件では、内部からの告発がなければ問題は表面化しなかったとされています。
しかし、企業側が内部告発を押さえ込もうとする姿勢を見せていたことが、社会的な反発を招いています。
内部告発者はしばしば不利益な扱いを受けることがありますが、公益通報者保護法などの制度はそのような通報者を守るために存在しています。
企業がこの制度の趣旨を理解し、健全なガバナンスを実現することが求められます。
厚生労働省の対応と今後の展望
厚生労働省は今回の事態を重く受け止め、都道府県との連携のもとで情報収集を続けるとしています。
また、医療機関側に対しても、外部の関係者が手術に関与する場合のルール整備や監視体制の強化を求める動きが強まりそうです。
再発防止のためには、企業単位での内部監査だけでなく、国による監視機能の強化や、内部告発制度の実効性向上も課題となります。
社会的信頼の回復に向けて求められる姿勢

ニューベイシブジャパンに対する社会の目は、今後も厳しいままでしょう。
違法行為を見逃してきた企業体質の改革、ガバナンスの強化、そして何よりも患者や医療従事者の安全を最優先とする姿勢が、今後の信頼回復の鍵となります。
また、今回の事件を通じて、医療機器業界全体の慣行や規範についても見直しが求められています。
単なる個別の不祥事として片付けず、業界全体での再点検と制度改善につなげていくことが必要です。
まとめ
- 医療機器企業の営業社員が、医療行為に関与することの危険性が浮き彫りとなりました。
- 社長による証拠隠し指示の疑いは、企業倫理を問う深刻な問題です。
- 内部告発を抑圧するような企業体質には、強い社会的批判があります。
- 厚生労働省は今後も情報収集と、対応強化を進める構えを見せています。
- 医療の安全性確保には、制度と企業体制の両面からの見直しが必要です。






