企業が利益を出しているにもかかわらず人員削減を行う黒字リストラは、近年ますます増加しています。
現在、大企業のリストラが加速しています。以前は赤字企業が主体でしたが、令和の時代では黒字企業でも人員削減が一般化。
この動きに対し、労働者の権利や企業の倫理、そして法律上の扱いが注目されています。
本記事では黒字リストラの合法性や企業側の論理、そして労働者が直面する課題について解説します。

黒字リストラの違法性は?
黒字リストラは原則として違法ではありません。
企業が利益を出していても、事業再編や将来の収益悪化を見据えた人員整理を行うことは、経営判断の範囲内とされています。
ただし、整理解雇に該当する場合には、厳格な条件が求められます。
整理解雇が有効とされるためには、裁判所が提示する以下の四要件を満たす必要があります。
一つ目は人員削減の必要性です。黒字でも中長期的な業績見通しが悪化していれば、この要件は認められる可能性があります。
二つ目は解雇回避努力義務で、配置転換や希望退職募集を経ることが求められます。
三つ目は人選の合理性で、解雇対象者の選定が恣意的でないことが必要です。
最後に、四つ目として解雇手続の妥当性があり、労働者との協議や説明責任が課せられます。
これらを欠いた黒字リストラは、違法と判断される可能性があります。
黒字リストラの謎
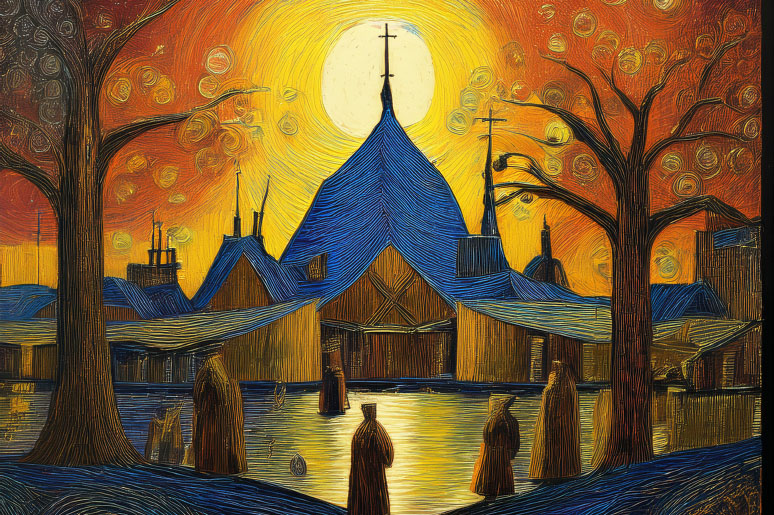
黒字リストラの背景には、将来を見据えた経営の効率化があります。
デジタル化や自動化の進展により、従来の業務や人員構成では競争力を維持できないと考える企業が増えています。
また、投資家や株主への説明責任も理由に挙げられます。経営指標の改善や株価の上昇を目指すため、利益が出ているうちに固定費を削減する戦略をとるケースがあります。
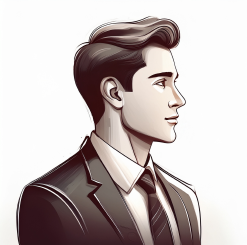 社労士のリク
社労士のリク「黒字でもリストラできるのは、日本の労働法が“経営の自由”も尊重しているからなんだ。だけど、説明責任は忘れずにね」
リストラを行った大企業
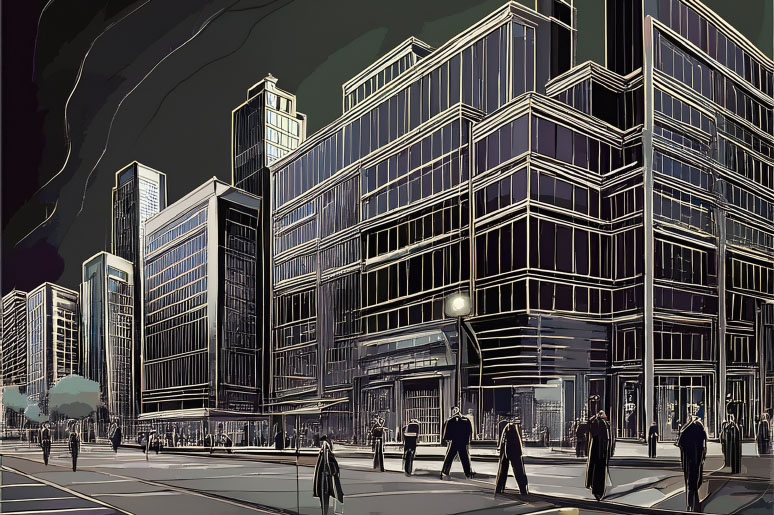
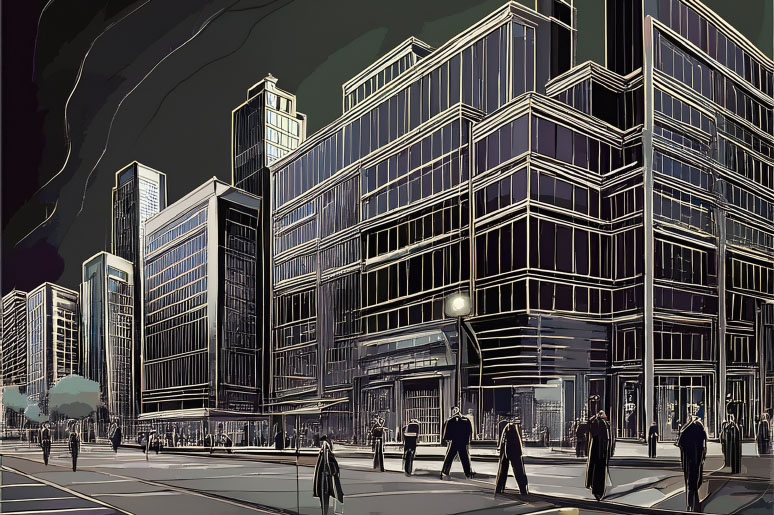
黒字リストラを実施した代表的な大企業としては、富士通、NEC、東芝、ソニー、パナソニックなどが挙げられます。
これらの企業はいずれも一時的に黒字を計上している状況であっても、将来の市場変化に備えた構造改革として希望退職の募集や早期退職制度を導入しています。
特に富士通は複数回にわたり黒字リストラを実施しており、その都度「先行投資のための人員適正化」という説明がなされてきました。
またNECは、黒字にもかかわらず営業部門の見直しを行い、大規模な希望退職を募りました。
これらの事例に共通するのは、短期的な業績ではなく中長期の競争力や経営資源の最適配分を重視した判断であるという点です。
- 富士通 複数回の希望退職を黒字中に実施
- NEC 営業部門の再編に伴う削減
- 東芝 構造改革に伴うグローバル人員整理
- ソニー 事業選別の一環として対象者を絞り込み
- パナソニック 部門統合による中高年層を中心とした削減
パナソニックのリストラ人数
パナソニックは過去に数回にわたりリストラを実施しています。
直近では、グローバル市場における再編や部門統合に伴い、国内外でおよそ一千人規模の希望退職者を募ったとされています。
この数字は公式発表ではなく、報道を通じて明らかになったものです。
同社は利益を確保している期間であっても、収益性の低い部門や重複した機能の整理を進めており、そうした施策の一環としてリストラを位置づけています。
対象となったのは主に管理部門や中高年層の社員であり、再雇用支援やキャリアコンサルティングも同時に実施されました。
このように、黒字でも事業再編を理由とした人員削減が現実に行われていることが分かります。
正社員はクビにできない?


日本の労働法制では、正社員の解雇は非常に厳しく制限されています。
労働契約法第十六条では、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は無効と定められています。これは労働者の生活と権利を保護するための措置です。
加えて、正社員は無期雇用であるため、企業側が一方的に雇用契約を終了することが難しいのが現実です。
雇用維持が強く求められる背景には、日本型雇用慣行と呼ばれる長期雇用制度の文化もあります。
そのため企業が人件費を削減したい場合は、非正規雇用の調整や希望退職の募集といった間接的な手段に頼らざるを得ません。
これは日本の労働市場における重要な構造的特徴であり、グローバル基準と比較すると雇用の流動性が極めて低いとされています。
リストラで退職金無しは違法なのか
リストラに際して退職金を支給しないことは、必ずしも違法とは限りません。
企業の就業規則や退職金規程に基づいて判断されるため、規定で「自己都合退職には支払わない」と明記されていれば、法的には正当とされることがあります。
ただし、希望退職制度の下では、早期退職に応じた社員に対して退職金の上乗せが行われるのが通例です。
これは退職を促すためのインセンティブであり、企業が強制的に解雇を避ける代替策でもあります。
一方で、整理解雇であれば、退職金を一切支給しないことが社会通念上不相当と判断されることもありえます。
特に長年勤続してきた正社員に対して一方的に退職金を支給しない場合は、労働審判や裁判で争われることが多くあります。
したがって、リストラに伴う退職金の有無は、個別の事情や規定内容によって異なるため、専門家への相談が重要となります。
まとめ
- 黒字リストラは、法律違反とは限らず条件次第で合法です。
- 将来の競争力確保や株主対策が、黒字リストラの背景です。
- 富士通やパナソニックなど大企業でも、実施されています。
- パナソニックでは、千人規模のリストラが報道されました。
- 正社員の解雇は、法律と雇用慣行によって厳しく制限されます。
- 退職金無しは一概に違法とは言えず、個別の判断が必要です。








